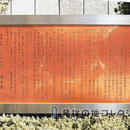大学 発祥地
だいがくはっしょうち
都営地下鉄三田線 神保町駅のすぐ南の学士会館(千代田区神田錦町3丁目28)前に「東京大学発祥の地」の石碑があり、脇に銅色の説明看板が設置されている。
明治10年(1877)、この地にあった東京開成学校と東京医学校が統合され、当地に東京大学が創立された出来事は、その象徴である。
明治維新後の日本は、欧米列強に追いつくため、早急に国家を近代化する必要に迫られていた。そのためには、西洋の高度な学術知識を取り入れ、それを研究・教授できる専門機関が不可欠であった。東京大学は、この国家的な要請に応える形で設立され、法学、理学、文学、医学といった多岐にわたる学問分野を統合した。これにより、従来の断片的な学問所とは異なり、体系的な知識と研究、そしてその成果に基づいた教育を行う、近代的な「大学」の基礎が築かれたのである。
この地から始まった東京大学は、西洋の大学制度を本格的に導入し、それを日本の実情に合わせて発展させていく先駆的な役割を担った。それは単に一つの学校ができたというだけでなく、近代日本の官僚、医師、技術者、学者など、各分野の専門家を育成する中核となり、日本の近代化を強力に推進する原動力となった。この看板は、日本の知的基盤がこの地で形成され始め、それが今日の日本の発展に繋がる礎となったことを静かに物語っている。
写真
碑文
我が国の大学発祥地
当学士会館の現在の所在地は我が国の大学発祥地である。
すなわち、明治10年(1877)4月12日に神田錦町3丁目に在った東京開成学校と神田和泉町から本郷元富士町に移転していた東京医学校が合併し、東京大学が創立された。
創立当所は法学部・理学部・文学部・医学部の4学部を以て編成され、法学部・理学部・文学部の校舎は神田錦町3丁目の当地に設けられていた。
明治18年(1885)法学部には文学部中の政治学及び理財学科が移され法政学部と改称され、また理学部の一部を分割した工芸学部が置かれた。このようにして東京大学は徐々に充実され明治18年までに本郷への移転を完了した。
したがって、この地が我が国の大学発祥地すなわち東京大学発祥の地ということになる。
明治19年3月東京大学は帝国大学と改称され、その時、それまで独立していた工部大学校と工芸学部が合併され工科大学となり、その後東京農林学校が農科大学として加えられ、法・医・工・文・理・農の6分科大学と大学院よりなる総合大学が生まれ帝国大学と名づけられた。
更に、明治30年(1897)には京都帝国大学の設立に伴い、東京帝国大学と改称された。
爾後明治40年に東北帝国大学、明治44年に九州帝国大学、大正7年に北海道帝国大学、昭和6年に大阪帝国大学、昭和14年に名古屋帝国大学が設立された他、戦後なくなったが大正13年に京城帝国大学、昭和3年に台北帝国大学がそれぞれ設立された。
昭和22年(1947)に至って、右の7帝国大学はそれそれ東京大学、京都大学、東北大学、九州大学、北海道大学、大阪大学、名古屋大学と呼称が変更された。
明治19年7月創立の学士会は以上の9大学の卒業生等を以て組織され、その事業の一つとして、当学士会館を建設し、その経営に当たっている。
平成3年(1991年)11月 学士会