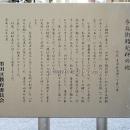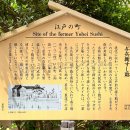与兵衛鮨 発祥の地
よへえずしはっしょうのち
両国橋の近く, 両国幼稚園の向かい側に“ベベ”というビルがある。 その建物の前に車道に向かって発祥の地を示すステンレスの案内看板が建っている。この発祥の地の碑は, 「与兵衛鮨」という店の発祥を表していると同時に, 「にぎり鮨」の発祥をも表している。
かつて「すし」と言えば 上方風の「押しずし」だったが, 文政の初年(1818年頃)に小泉与兵衛が江戸前の「にぎり鮨」を考案した。 最初は岡持にいれて行商, 次いで屋台での営業をした。新鮮なネタをその場で握る鮨が江戸っ子の好みにマッチし, また屋台に不似合いな当時高級品だった山本のお茶を出したりして大ヒットとなった。まもなく「華屋」という店を構えるようになった。 これが江戸前鮨を代表する「与兵衛鮨」である。
その後 与兵衛のにぎり鮨を真似る店が江戸中に広がり, 一方 大阪ずしは衰えて一時は全く影をひそめたという。
華屋の与兵衛鮨は昭和5年(1930) に廃業した。 最近「華屋与兵衛」というレストランチェーンが繁盛しているようだが, 元祖 与兵衛鮨の名前を借りただけで 直接の関係はないらしい。
当地から徒歩1分ほどの春日野部屋(墨田区両国1丁目7-11)入口近くには、与兵衛すし跡を示す立札がある。
写真
碑文
与兵衛 鮨 発祥の地所在 墨田区両国一丁目八番
この横町の左手に, 江戸握り鮨発祥といわれる与兵衛鮨がありました。文政の初めに, 初代・小泉与兵衛(一七九九 ~一八五八)により大成されました。
小泉与兵衛は, 霊岸島の生まれでしたが, 次々と商売を替えて, 本所で暮らすようになりました。その頃に, 大阪風の押し鮨にあきたらず, これを江戸風に鮮度を保ち, 手早く造る方法を工夫しました。始めは, 毎日岡持に鮨を入れて売り歩きましたが, 評判を呼ぶようになり, 屋台を出し, 後には店舗を開くほどになり, 殺到する注文に追いつけない繁盛ぶりだったと伝えられます。
当時の狂歌 にも「鯛比良目 いつも風味は与兵衛ずし買手は見世にまって折詰」などと人気のほどを伺うことができます。
また, 食通の武士の注文に応じて与兵衛が創案した「おぼろの鮨」も大変な人気となりました。屋台で山本のお茶を出したことも人気に拍車をかけました。
以後, 昭和5年に惜しくも廃業しました。平成一二年三月
墨田区教育委員会
江戸の町
Site of the former Yohei Sushi与兵衛すし跡
27
現代に伝わっている江戸前の握り鮨ができたのは、約二百年前の文政年間で、小泉与兵衛が考案したといわれています。
当時は鮨といえば大阪風の押し鮨ばかりだったところを、酢で締めた飯の上に、ワサビをはさんでネタを乗せて握られたものを屋台で立喰いするという新しいスタイルは、一挙に江戸っ子の人気となりました。
与兵衛は、握り鮨を岡持ちに入れて盛り場を売り歩くことから始め、屋台、裏店での店売りを経て、文政七年(一八二四)に元町(両国一丁目)に「華屋」という屋号の店を開き大繁盛しました。この成功によって鮨屋という形態が確立し、その軒数が増えるに従って、職人が腕を競うようになり、一大食文化を築きました。墨田区